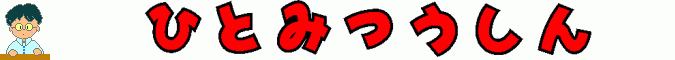

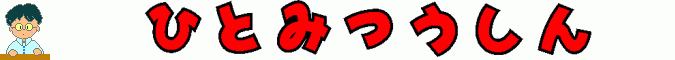
|
16号 特集〜散瞳:さんどう 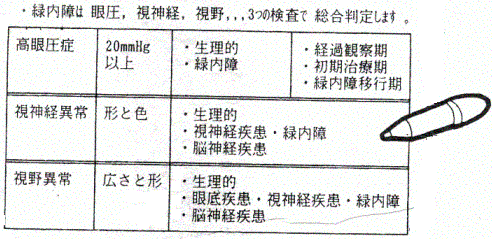
ここから本文です。。
白目の中央に黒目があります。この黒目の中央をよく見ると穴があいています。これが瞳孔です。この瞳孔はカメラの絞りのようなもので、明るいと縮み、暗いと広がり、その直径は自動的に常に変化していて眼内にはいる光の量を微調節しています。 この瞳孔は眼内を覗くことができる唯一の窓でもあります。眼内の網膜や視神系を直視するにはこの窓を経由する以外に方法はありません。診察のためにはその窓はできるだけ広い方がよいわけで、江戸時代の眼科医にとっては、散瞳薬は夢の薬だったそうです。シーボルトはこの散瞳薬とひきかえに日本地図を手に入れたとも聞いたことがあります。 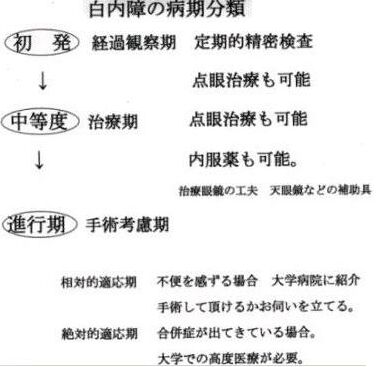
眼底を検査することは散瞳しなくてもある程度は可能で、人間ドックの眼底検査はこの散瞳しない方法をとっているところが多いようです。これは鍵穴からから部屋のなかを覗くような方法で眼底中央部の決まった場所だけをねらって検査するものです。 内眼の全範囲をくまなく調べる精密検査の場合には散瞳が必要不可欠なものです。通常は散瞳薬を点眼して20〜40分効かせた上で検査に入ります。窓は開いた状態ですが肉眼では見えませんし、眼底中央部と周辺部ではまた違うので、いろいろなレンズを用います。また硝子体や水晶体の診察には独特の道具が必要です。 一言で眼底と言いますが、目の中は立体的で複雑な構造をしていて、くまなく全部調べあげるのはけっこうたいへんな作業です。 まぶしいわ、目薬でべちゃべちゃにはなるわ、、、しかも薬は4〜5時間効いていて、その間手許がピンぼけだし、車の運転はしてはいけません。しかしこのような正式の精密検査を受けるチャンスは一生のうちそう何回もあるものではありません。 その意味で症状は片目だけでも両眼を同時に検査を受けておくことはよいことで、瞳を開いて眼底の検査をしましょうと言われた場合には、ついでですからと両眼を調べてくれるよう医師に頼んでおくのは賢い知恵でしょう。
内眼の病気は症状がでる前に発見可能で予防治療ができるものが、たくさんあります。一病息災。 屈折と言われても分かりにくいですね。近視とか遠視、乱視の度数のことです。だいたいの度数を調べることは、散瞳しなくても視力検査で可能です。大人の診察の場合にはほとんど、通常の視力検査による方法ですんでいます。 ところが子供の場合には視力測定による方法だけでは不正確なことが多く見うけられます。まだお答えのできないベビーでは視力検査じたいできません。大人でもなんらかの内眼疾患や斜視など持っていると屈折が不安定で測定できないことがあります。 そのようなとき散瞳して屈折をはかると安定した数字がはかれます。眼鏡の処方も正確になり、確定診断とも言えます。 実際には、当日はこの検査だけで終了し、後日眼鏡処方決定のための練習に再診することになります。 学童の視力測定の原因の一つに調節緊張と言う病態があります。視力測定をすると、遠方視力低下、近方視力正常、屈折はマイナス側と一見近視と同じような結果がでますが、データが不安定なのが特徴です。 常にピントを手許に合わせようとする無意識的な習慣のようなものと思えばよいでしょう、程度の強い場合、調節痙攣と言います。結果的に近視と似た症状となるのですが、真の近視かこの調節緊張なのかは先に述べた精密屈折検査で確定診断します。 昔の言葉で言う仮性近視と言うと分かりやすいでしょうか。この治療に使われるのが調節麻痺剤の点眼薬です。瞳を開き、目の緊張をやわらげて休ませる薬です。散瞳の効果がありますので一回の点眼で4〜5時間はピンぼけになります、ミドリンMという薬が最もよく使われています。昼間に使用すると勉強のさまたげになること多いので夜練る前に一回だけ点眼すると言う処方が多いです。 虹彩炎という目の中の炎症の治療に活躍するのがやはリ散瞳薬です。この病気は長く続くと虹彩が固着し、動かなくなるという合併症がでることがあります、この状態が進展すると緑内障をひき起こすこともありますので要注意です。 これを予防するためには炎症をおさえる治療と同時に、散瞳薬を用いて虹彩を休ませ固着を予防することが大事です。これもまた点眼するとピンぼけな感じになありますが治療のためなのでちょっとガマンです。 散瞳はなじみのないものですがこれを機会に覚えておいて損はありません。 ( ひとみつうしん 16号 終了。平成10年1月20日) |
HOME 飛蚊症 緑内障 アトピー 白目 視力回復 遠視 弱視 網膜剥離 眼科問診表 巨大乳頭結膜炎 眼精疲労 ぶどう膜炎 アレルギー性結膜炎 眼科受診のコツ 白内障 散瞳 眼科診療Q&A メールマガジン